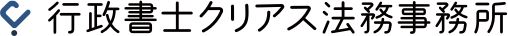お知らせ
令和7年度版: 小規模事業者持続化補助金〈一般型・災害支援枠〉(9次) 公募要領を徹底解説 〜被災事業者必見!申請ポイントと最新変更点〜

被災を受けた小規模事業者にとって、販路回復・事業再建を支援する「小規模事業者持続化補助金〈一般型・災害支援枠〉」は、重要な資金サポート策です。
今回、9次公募(「9次受付締切分」)に向けた公募要領が発表され、申請を検討している事業者にとって“押さえておきたいポイント”が多数あります。
本記事では、最新版公募要領の概要、申請対象・要件、支援内容、申請時の注意点、そして“採択を有利に進めるためのポイント”を分かりやすく整理します。
まず、最新の状況を整理します。
中小機構(日本政策金融公庫・商工会議所等と連携する中小企業支援機関)より、令和7年5月16日付けで「一般型・災害支援枠」の公募要領が公開されています。
「令和6年 能登半島地震・ 奥能登豪雨」など、特定の被災事案を対象とする枠組みとなっており、被災地域・事業者の再建・販路回復を支援することが目的です。
多くの資料によれば、申請受付期間・締切・支援機関確認書の発行期限などが段階的に設定されており、申請を予定する事業者はスケジュールを早めに確認しておく必要があります。
なお、各「次回」公募(6次・7次・8次)においても「公募要領改定版」が複数回公開されており、9次においても変更点がある可能性があります。
申請時には最新版の公募要領を必ず確認してください。
「災害支援枠」では、被災した小規模事業者が主な対象です。
具体的には、被災地域(例:石川県、富山県、福井県、新潟県)に所在し、令和6年能登半島地震・奥能登豪雨などの被害を受けた小規模事業者等。
小規模事業者の定義(業種別・常時使用従業員数等)を満たしていること。例えば、商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)で常時使用する従業員が5人以下、サービス業のうち宿泊・娯楽業で20人以下、製造業その他で20人以下など。
補助金を申請するにあたって、被災状況・売上減少・復旧又は販路回復に向けた具体的な計画を有していることが条件となります。
主な補助・対象経費としては次の通りです。
補助対象経費には、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、借料、修繕・設備処分費、委託・外注費、車両購入費などが含まれています。
特例措置として、災害発生後に交付決定前であっても「適正と認められる事業」に対して、交付決定前に行った事業についても対象となる場合があることが明記されています。
補助率・補助上限額等については公募要領に具体的な数値が記載されていますが、各回・各枠で異なっているため、最新版を確認することが必要です。
申請を行ううえでの流れの概略としては以下の通りです。
🔶 被災事業者であること・対象地域であることを確認
🔶 経営計画・事業再建/販路回復計画を策定
🔶 支援機関(商工会・商工会議所など)に「支援機関確認書」を発行してもらう
🔶 電子申請システム(例えば J‑グランツ など)または所定の申請書類を準備・提出
🔶 審査・交付決定・事業実施・実績報告・補助金交付、という流れとなります。
申請締切・支援機関確認書の発行期限などのスケジュールが、- “申請締切日の数週間前” には準備を始めることが望ましいとされています。
9次公募を検討するにあたって、過去回からの変更点・留意点を以下に整理します。
最新版要領の確認:公募要領は第版(第〇版)として改定されており、過去版では受付けられません。必ず最新版をダウンロードして確認しましょう。
支援機関確認書の発行期限:過去回では、申請に先立ち “支援機関確認書” の発行が必須で、その発行期限が申請期限より前に設定されていました。申請前に必ず支援機関に依頼しておきましょう。
事前着手の制限:公募要領では、原則として交付決定前の契約・支払い・着手は対象外とする規定があるため、準備段階から補助対象経費の契約や購入をしないように注意が必要です。
災害特例対応:災害支援枠特有の特例として、交付決定前であっても「適正と認められる」場合には対象経費となる可能性がある規定があります。該当災害の発生日・地域・被害状況を確認してください。
重複申請・過去実績の報告義務:過去に同種の補助金(一般型・通常枠、他の特別枠など)を受給している場合、実績報告の提出が条件となるケースがあります。申請前に過去受給状況を整理しておきましょう。
提出書類・証憑の整備:領収書・請求書・通帳等支払い状況が確認できる資料の保管・提出が前提とされており、「現金支払」「記録不備」は審査上マイナスになる可能性が高いです。
申請を成功させるためには、次のようなポイントに配慮すると良いでしょう。
被災状況・影響の整理:災害でどのような被害を受けたか(施設・設備・販路・売上減少等)を具体的に整理し、事業再建・支援対象であることを明確にします。
再建・販路回復の計画が明確かつ実行可能か:補助金は「事業をどう再生・発展させるか」に使われるため、計画内容(何を、誰に、どのように)を明記しましょう。単なる設備購入だけでなく、「それによってどう売上・利益が改善するか」の見通しを書き込むことが重要です。
支援機関との連携を早めに確保:商工会・商工会議所など、支援機関との相談・確認を早期に行い、「支援機関確認書」の発行準備を進めておきましょう。
証憑・経費管理の事前準備:補助対象経費となるかどうか、契約・支払い・納品・領収書など証明できる体制を整えておくこと。現金支払い・記録不備は避けるのが鉄則です。
スケジュール管理を徹底する:申請締切・支援機関確認書発行期限・交付決定までの流れ・事業実施期限を逆算して準備しましょう。
「小規模事業者持続化補助金〈一般型・災害支援枠〉(9次)」は、被災した小規模事業者が早期に事業再建・販路回復を図る上で有効な支援制度です。
しかし、申請には「被災対象要件」「経営計画・再建計画」「支援機関確認」「適正経費」「証憑整備」「スケジュール管理」など、押さえるべきポイントが多くあります。
公募要領の最新版を確認し、申請準備をしっかり行えば、採択の可能性を高めることができます。