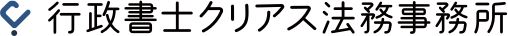お知らせ
実地指導?監査?どっちがどっち??違いについて紹介

「放課後等デイサービス事業」や「就労支援事業」を運営されている皆さまにとって、行政からの「実地指導(運営指導)」や「監査」といった外部チェックは、日々の事業運営における重要なターニングポイントとなります。
今回は大阪府・大阪市エリアにおける最近の動きを踏まえながら、両者の違いや実務上のポイントを整理し、事業者として押さえておくべき点をブログ形式でお伝えします。
まず、放課後等デイサービスや就労支援等の障害福祉サービス事業者に対して行われる「実地指導(現在は「運営指導」と表記されることが多い)」について整理します。
実地指導(運営指導)とは、事業所が法令・条例・指定基準に基づいて適切に運営されているかを、指定権者(都道府県・政令指定都市・市町村など)が直接または間接的に確認するものです。
例えば、サービスの質、給付費請求の適正性、人員・設備・運営体制の基準順守などが対象になります。
大阪市では「大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課」が実地指導・監査を実施する体制を規定しています。
通常は 概ね3年に1回 程度が目安とされており、事前通告があることが一般的です。
ただし、利用者からの苦情、多数の指摘歴、報酬請求の疑いなどがある場合には、 随時・抜き打ち の実地指導が行われることもあります。
形式としては「書類提出+現地訪問」「ヒアリング」「施設内の視察」などが含まれ、出勤簿・勤務表・利用契約書・個別支援計画などの帳票類が重点的に確認されます。
以下は、放課後等デイサービス事業所において実地指導でよくチェックされる項目です。
●人員配置・職員の資格・勤務実績(シフト・タイムカード)
●利用契約書・重要事項説明書・個別支援計画の作成・説明・同意手続
●サービス提供記録・送迎記録・研修記録・事故・ヒヤリハット報告など
●加算・減算要件の適正な算定
●会計区分・帳票管理・賠償保険などの運営管理体制
こうした確認を通じて、事業所の運営が適正であるか・改善が必要かという“診断”的な意味合いを持ちます。
次に「監査」の意味・特徴を整理します。
監査とは、上記の運営指導で確認された事項以上に、 指定基準違反・報酬請求の不正・虐待等重大な事案 が疑われる場合に、より強い行政措置を伴う手続として実施されるものです。例えば、給付費請求が不正だったと認められれば返還や加算金支払い、最悪の場合、指定取り消しに至る可能性があります。
大阪市の要綱では、以下のように定められています。
監査は、「利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき」「指定基準又は報酬算定基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき」「実地指導等を行っても改善がみられないとき」等に随時実施する。
通常は事前通知文書により実施されますが、緊急性がある場合には当日通知・抜き打ちという形がとられることもあります。
監査では、事業所の管理者・従業員への質問、利用者・保護者からの聴取、関係帳票の預かり・写し取得など強制的・広範な調査が行われます。
監査結果として、改善指導だけではなく「過誤請求の返還」「行政処分」「指定取消し」などの措置につながる点で、運営指導とは明確に異なります。
ここではポイントを改めて整理します。
| 実地指導(運営指導) | 監査 |
| 主な目的 | 運営実態の確認・改善支援 | 違反・不正の事実確認・行政措置 |
| 実施タイミング・頻度 | 概ね3年に1回/定期・予告ありが多い | 違反疑い・改善なし・通報などで随時/予告なしもあり得る |
| 対象範囲 | 全ての事業所が対象になり得る | 重大な疑いがある事業所に限定される可能性高 |
| 対応性 | 指導・助言が中心、協議的な側面あり | 強制的・摘発的な側面あり、処分リスクあり |
| 事業者への意味合い | 日々の運営チェック・改善機会 | リスクの顕在化、最悪ケースは指定取消し等の重大処分 |
このように、実地指導が「運営を良くするための機会」という意味合いが強いのに対し、監査は「問題があると認められた場合に実行される厳格な手続き」であるという点が肝です。
大阪府・大阪市の資料から、実務的な“現場の動き”を見てみましょう。
大阪市の実施要綱
大阪市の「障がい福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱」では、実地指導(実地に事業所を訪問して行う)と監査の区別が明文化されています。
特に、監査の実施要件として「実地指導を実施しても改善がみられないとき」「不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき」などが挙げられています。
大阪市・大阪府の公表資料より、最近の指導・監査でよく見られる指摘事項などが確認できます。
例えば、
🔷 個別支援計画の原案に対する利用者・家族の「同意」手続が抜けていたという指摘。
🔷 書類の整備・保存が不十分であった(例:出勤簿・タイムカード・研修記録)という指摘。
🔷 会計処理・報酬請求・帳票管理に不備があり、過誤請求等との連鎖リスクが指摘されている。
🔷 集団指導(講習形式)への参加不足などから、指導対象にされるケースも。
実践的には、実地指導中・直後に「重大な基準違反」や「報酬請求の不正疑い」が確認され、「その場で監査に移行」した事例も報告されています。
大阪エリアでは、例えば会計・帳票管理といった運営体制の甘さが監査に至る指摘項目として散見されます。
府・市の「指導監査フロー図」でも、「運営指導→改善→改善なし→監査」という流れが示されており、運営指導を“問題がなければ終了”とみなさず、改善を確実に行うことが重要です。
運営指導・監査という“制度的な枠組み”を理解したうえで、実務的に事業者として備えておきたいポイントを整理します。
①帳票・書類の整理は日頃から
• 職員の勤務表・タイムカード・雇用契約書・資格証・研修記録など、人員配置/職員管理にかかわる帳票は、実地指導時の核心となる確認項目です。
• 利用契約・重要事項説明・個別支援計画・サービス提供記録・苦情・事故記録など、サービス提供実態に関する書類も整備を欠かせません。
• 会計処理・事業ごとの収支区分・保険・設備・災害訓練記録など、運営体制全体に関して“証跡”が残せるようにしておきましょう。
②人員・加算要件・基準順守を確認
• 勤務シフト(予定・実績)、常勤・非常勤の換算、職員配置人数など、基準人員を守れているかを定期的にチェック。
• 加算算定要件(専門的支援加算、送迎加算など)を満たしているのか、また減算要件に該当していないかを必ず確認。
• 運営規程やサービス実施体制(例:学校・医療機関との連携、児童の安全確保)など、基準だけでなく「質」の観点も問われる時代になっています。
③「改善可能な指導」であることを意識
実地指導は、単なる「チェック」ではなく「改善の機会」として捉えることがポイントです。
指摘を受けたら、改善計画を立て、実践・記録・フォローアップを行うようにしましょう。
特に、実地指導で指摘を受けた項目が是正されないまま放置されると、監査に発展するリスクが高まります。
④監査に至るリスクを理解しておく
監査となると、書類提出だけでなく、現場ヒアリング・実地検査・場合によっては利用者・保護者への聴取まで実行される可能性があります。
指定取り消し・給付費返還・加算金支払い・過誤請求リスクなど、経営・事業継続に深刻な影響を及ぼします。
したがって、「緊急連絡先を整備」「抜き打ち対応シミュレーション」など、日常的な備えも有効です。
⑤大阪府・市の最新動向をチェック
大阪府・大阪市では、令和7年度における指導監査の方針や資料が公表されており、法令遵守・運営管理・虐待防止・身体拘束適正化などに関して“重点事項”が示されています。
特に「身体拘束・虐待防止」「ICT活用による帳票管理」「学校・医療機関連携」などが今後さらに注目される傾向です。
今回は主に放課後等デイサービスを例に説明しましたが、就労支援事業(例:就労継続支援A型・B型・移行支援)も、実地指導・監査の枠組みや要点は同様です。
以下、特に押さえておきたい点を挙げます。
🔶 就労支援では「就労移行・訓練実績」「利用者の勤務先定着」「工賃」「施設外就労の実績」などサービス実績が問われることが多く、帳票・記録の整備が重要です。
🔶 人員配置・支援体制・専門スタッフ配置(就労支援員・職業指導員等)についても基準が細かく、実地指導での確認対象になります。
🔶 加算・減算の要件(例:定着支援加算、訓練加算など)を満たしているかも着目されるため、制度理解が必須です。
🔶 運営指導・監査で指摘された就労支援事業所では「個別支援計画・モニタリング記録」が不備であったというケースもあります。
放課後等デイサービスと同様に、就労支援事業も「実地指導=日常運営のチェック」「監査=リスク顕在化時の厳格な確認」という枠組みで捉えておくと、対応がしやすくなります。
実地指導(運営指導)は、事業所運営を振り返り・改善する機会という位置づけ。定期的・通知ありが一般的です。
監査は、重大な基準違反・不正が疑われる場合に実施され、処分リスクを伴う強い手続きです。
大阪では、帳票管理・人員基準・契約・加算要件・改善履歴などが指摘事項として目立っています。
日常的な運営管理・帳票整備・職員研修・モニタリング体制を整えておくことで、実地指導・監査ともに安心して対応できます。
就労支援事業においても同様の枠組み・ポイントがあり、サービス種類に応じた対応が必要です。
指導や監査におびえてしまうのではなく、これを“事業運営をより良くするチャンス”と捉えて、日頃から準備を整えておくことが肝要です。