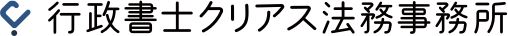お知らせ
【注意喚起】福祉事業所での加算運用事例から学ぶ、実地指導・監査で注視されるポイント

障害福祉サービスや放課後等デイサービス、就労支援事業を運営されている皆さまにとって、行政からの「実地指導」や「監査」は決して他人事ではありません。
日々話題になる事件は発生しており、最近でも制度の加算運用に関する疑義が報道され、業界内で大きな話題となりました。
今回は報道内容をベースに、実地指導・監査の現場で特に注意すべき運用実態を考察し、日常の運営で注意すべきポイントを整理します。
▶️ 報道の概要
2025年11月、大手障害福祉サービスグループが、一部報道で以下のような疑義を指摘されました。
・就労継続支援A型事業所と放課後等デイサービスを複数運営
・利用者をA型事業所に一時的に雇用後、短期間で退職・再利用を繰り返すことで、加算取得(例:就労移行支援体制加算など)を実質的に繰り返していた疑い
・雇用契約や実際の労働の実態が乏しく、形式的に雇用関係を作り出していたという声も
法人側は「行政機関と連携の上で運営してきた」「誤解を招く部分については是正を行う」と説明。
▶️ なぜ問題となったのか?
このケースでは、「制度の趣旨に則った運用であったかどうか」が問題視されています。
たとえ書類上は合法であっても、「実態が伴っていない」と判断された場合、監査対象となるリスクが高まります。
以下は本事案をベースにした当事務所経験からの推察事項を含みます。
① 書類整備は整っていても「実態の乏しさ」があるケース
書面上では雇用契約、勤務実績、支援計画の整備がなされていても、以下のような点がチェックされます。
・雇用期間が極端に短く、実際の職業訓練や支援が行われていない
・支援員によるモニタリング記録が形式的で内容に乏しい
・利用者本人が制度の運用目的を理解していない
実地指導では、「形式」と「中身」のバランスが問われます。
帳票類の整備だけで安心せず、実際にどのような支援がどのように行われていたかの実証が不可欠です。
② 加算目的が疑われる“利用者のローテーション”
今回の報道でも疑問視されたように、同一法人内で以下のような運用が見られるとリスクが高まります。
・利用者を別の事業所へ「計画的にローテーション」させて加算取得
・雇用・退職・再利用を繰り返すことで、加算を複数回申請
・A型→就労移行→B型→再度A型など、支援計画の妥当性が説明できない移動
特に大阪市では、これまでの運営指導・監査において、「不自然な事業所間移動」が監査理由として挙げられる事例が複数あります。
③ 加算の“取得要件”を満たしていないのに申請している
次のような加算取得の実態は、監査で問題視されることが多いです。
・加算要件(職員配置・支援体制)を一部満たしていない
・実際の支援内容や利用者のニーズと加算内容が一致していない
・支援記録に具体性・連続性が欠けている
これらの問題は「過誤請求」と見なされ、返還命令や指定取消しにつながる可能性もあります。
▶️ 大阪市の監査要綱の強化
大阪市では、令和7年度の監査実施要綱において「事業者間の利用者移動」や「加算の過剰取得」などを重点確認項目に明記しています。
▶️ 府レベルでも“系列事業所の運用実態”が注目
大阪府は、複数事業所を展開する法人に対して「運営全体の透明性と整合性」を重視しており、支援内容・記録の一貫性や系列間の連携状況を詳細に確認する傾向があります。
✔️ 利用者ローテーションの透明化
・支援計画に「なぜ移動するのか」の明確な理由を記載
・利用者本人・家族の理解と同意をきちんと記録
✔️ 加算の“実態”に基づいた申請
・加算要件を月ごとに自己点検
・支援記録・モニタリング内容に具体性を持たせる
✔️ 雇用契約・就労訓練の真実性
・訓練内容の写真・報告書・成果記録などを残す
・実際の業務が訓練計画に沿っているかを定期チェック
2025年11月に報道された事例は、障害福祉事業者にとって非常に示唆に富む内容でした。
書面だけでなく支援の実態、利用者の動き、加算取得の合理性といった“本質的な部分”にまで目を向ける必要があります。
実地指導・監査は「摘発」ではなく、「改善」のチャンスでもあります。
日常的に運営を見直すことで、トラブルや処分リスクを回避し、安心・安定した事業運営を実現しましょう。